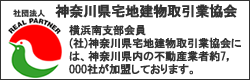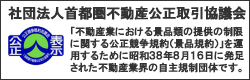このブログを読んでいるあなたにとっては当たり前の話かもしれませんが、
一般の方が不動産物件を検索するときによく使うのは、スーモですか?アットホーム、ホームズ、ヤフーのHPから…ですか?
どちらか、あるいは全部はないかと思います。
一方、一般のかたが見れそうで、見ることができない…不動産業者がIDとパスワードを使って入るサイトがあります。
それがREINS(レインズ=不動産流通機構)。
リアル・エステート(不動産の意味)のRE
インフォメーション(情報)のI
ネットワーク(網)のN
システム(機構)のS
アメリカでは古くからある流通システムでしたが、それを日本でも採用したというものです。
このIDとパスワードがあれば、北海道から沖縄まで、登録されている情報を全て検索することができます。
つまり目の前のお客さんが(そんなことはありませんが)沖縄と札幌にマンションが欲しいと言われても対応出来てしまうの
です。
全国のほとんどの不動産屋さんが、この情報網の中にいるので、不動産を見つけに地域の業者2~3軒まわっても、紹介される物件が同じ…ということになるのです。
駅などで無料で配布されているスーモ(住宅情報誌)で、同じ物件がずら~っと出ているのもその表れで、
もう、ほとんどの不動産情報は共有されているのですね。
 じゃ、どこの不動産屋に行っても全く同じなのか?というと、
じゃ、どこの不動産屋に行っても全く同じなのか?というと、
そうではないのです。
不動産とは唯一無二なもの。
レインズなり、アットホームなり情報網に載る前の状態というのを想像してみてください。
不動産業者は、例えば売り情報が出たら、まずは自分の顧客で契約ができないか?
それがダメなら同じ会社の他の営業の顧客で契約できないか?
を考えますよね?
そうすれば、売主からも、買主からも手数料が頂けるわけですし。
それでもダメなら、仲間の不動産業者に連絡してそこで契約できないか?
それでもダメなら情報網へ…ということに…なりますよね?
ま、いきなり出てきた物件を自社で契約できるというラッキーなケースは、
大手になれば確率は上がりますが、そうないものです。
検索サイトに出ている物件が“出がらし”…とは言いませんが、信頼できる不動産業者さんと仲良くなれば、
情報網に載る前の情報があなたにやってくることになります。
これって、すごいことなんですよ。